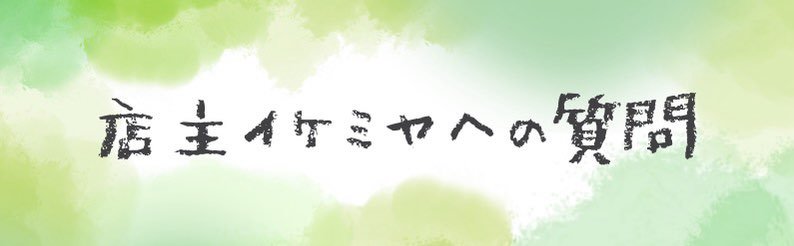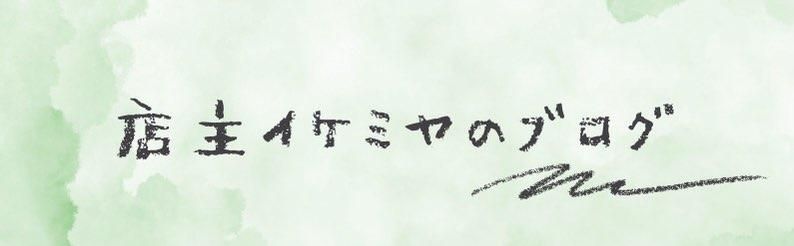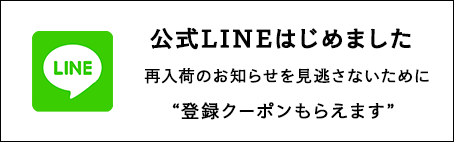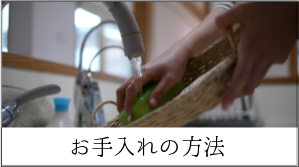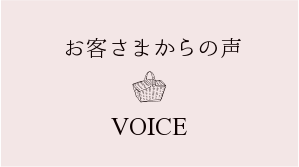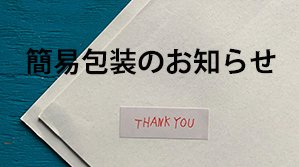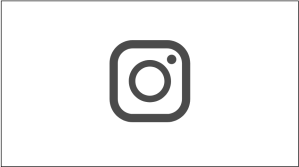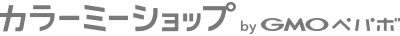<moily誕生のものがたり>
............................................................................................................................................................................................
2009年はじめて池宮がカンボジアに訪れたことからmoilyはじわじわスタートします。
カンボジアは「貧困」「可哀想」と勝手に思っていましたが
実際に関わったひとたちは、笑顔があふれる、他人を思いやるやさしくて温かい
豊かに生きる人たちでした。
その後、自分の目で世界を見たいと
アジア、中東、アフリカ、南米を1人で周り、ボランティアをしました。
しかし現地の中に入り込み
その土地の人たちと仲良くなればなるほど見えてくる山ほどの問題。
「身体を売らなけらば生活ができない同い年の友だち」
「お手伝いさんになるため、小学校をやめていく自分の生徒たち」
自分はなんて幸せに生きさせてもらってきたんだろう。
なんて自分は非力なんだろう・・・
なにか自分に力になれることはないか。
と日々悶々と考える毎日でした。
ボランティアだけでは解決できない問題にも打ち当たり
時には現地の人とケンカすることも。

※ネパールで小学校の先生をしていたころ
多くの経験をする中で私にできることは、
「現地のゆたかな暮らしはそのままで、そこに仕事を作ること」
と思いはじめます。
2014年にカンボジアに拠点を変え
まだ埋もれている手仕事で何かその国の力になるものはないか??
と自転車で真っ黒になりながらカンボジア中を走り回りました。
日本人と気づかれることはないくらい。笑

そのように走り回っている中、たまたま目についたのが、現地で野菜を売る時に使われているカゴでした。
「この形をもう少しアレンジして、品質もあげたら可愛いかもしれない!
それで一緒に収入も作れるんじゃないか?」
そんな思いつきから、職人探しが始まります。

ご縁をいただいた村に
何度も何度も通い
少しずつ職人さんとうちとけていきました。
わたしの思いをはなすと
「キレイにかごを作ることはできるけど、それを求めている人はいないし
かごを作っても安いんだよ」と。
「じゃあ一緒にきれいなかごを作ろうよ。わたしその分ちゃんと高く買うよ!」
そんな会話からうまれたmoilyのかご
今ではお互いの状況に合わせ
困った時は助け合いながらものづくりを行えている本当に良い関係です。

きれいなかごを作るためには
職人さんたちと一緒にさまざまな努力をしてきました。
色や形、素材の始末の仕方、素材の整え方など多くの決まりがあります。
それを外れてしまったものは作りなおし。
もちろんここまでくるまでに職人さんと何度も衝突しました。
「なんで一生懸命作ったのに、買ってくれないんだ!」というのがほとんど。
時には泣き出してしまったり、怒って辞めてしまったりした職人さんもいました。
伝えるこちらもみんなのことが大好きなので本当は言いたくないのだけれど
心を鬼にして何度も何度も理由を伝え
少しずつ品質が改善されていきました。
今では新しくカゴ編みを覚える若い子が出てきたり
他の村の職人さんもmoilyでかごづくりをしたいと訪ねてくるようになりました。
そうすると職人さんたちは
「わたしたちと一緒に作るならきれいに作らないとダメだよ!」なんて言ってるから
笑ってしまいます。かわいい。
村の収入も平均2.5倍ほど上がり(2020年時)、出稼ぎに出かける人はぐんと減り
職人さんたちは家族と共に村で生活しています。

moilyのカゴには作った職人さんの名前をつけています。
手編みで作るカゴは、人間らしさがみえる面白さがあります。
いくつかの厳しい品質チェックをクリアしてきたカゴでも、カーブの加減や、素材の選び方、編む時の力の入れ加減、絶対に同じものはありません。
性格やその時の感情が感じられて面白いんです。

ぜひ、カゴを手に取る時、遠いカンボジアで、
職人さんたちが笑いながら、ハンモックを揺らして子どもをあやしながら、
穏やかにカゴを編んでいる様子を想像してみていただけたら嬉しいです。
職人さんについてはこちらから
............................................................................................................................................................................................
2009年はじめて池宮がカンボジアに訪れたことからmoilyはじわじわスタートします。
カンボジアは「貧困」「可哀想」と勝手に思っていましたが
実際に関わったひとたちは、笑顔があふれる、他人を思いやるやさしくて温かい
豊かに生きる人たちでした。
その後、自分の目で世界を見たいと
アジア、中東、アフリカ、南米を1人で周り、ボランティアをしました。
しかし現地の中に入り込み
その土地の人たちと仲良くなればなるほど見えてくる山ほどの問題。
「身体を売らなけらば生活ができない同い年の友だち」
「お手伝いさんになるため、小学校をやめていく自分の生徒たち」
自分はなんて幸せに生きさせてもらってきたんだろう。
なんて自分は非力なんだろう・・・
なにか自分に力になれることはないか。
と日々悶々と考える毎日でした。
ボランティアだけでは解決できない問題にも打ち当たり
時には現地の人とケンカすることも。

※ネパールで小学校の先生をしていたころ
多くの経験をする中で私にできることは、
「現地のゆたかな暮らしはそのままで、そこに仕事を作ること」
と思いはじめます。
2014年にカンボジアに拠点を変え
まだ埋もれている手仕事で何かその国の力になるものはないか??
と自転車で真っ黒になりながらカンボジア中を走り回りました。
日本人と気づかれることはないくらい。笑

そのように走り回っている中、たまたま目についたのが、現地で野菜を売る時に使われているカゴでした。
「この形をもう少しアレンジして、品質もあげたら可愛いかもしれない!
それで一緒に収入も作れるんじゃないか?」
そんな思いつきから、職人探しが始まります。

ご縁をいただいた村に
何度も何度も通い
少しずつ職人さんとうちとけていきました。
わたしの思いをはなすと
「キレイにかごを作ることはできるけど、それを求めている人はいないし
かごを作っても安いんだよ」と。
「じゃあ一緒にきれいなかごを作ろうよ。わたしその分ちゃんと高く買うよ!」
そんな会話からうまれたmoilyのかご
今ではお互いの状況に合わせ
困った時は助け合いながらものづくりを行えている本当に良い関係です。

きれいなかごを作るためには
職人さんたちと一緒にさまざまな努力をしてきました。
色や形、素材の始末の仕方、素材の整え方など多くの決まりがあります。
それを外れてしまったものは作りなおし。
もちろんここまでくるまでに職人さんと何度も衝突しました。
「なんで一生懸命作ったのに、買ってくれないんだ!」というのがほとんど。
時には泣き出してしまったり、怒って辞めてしまったりした職人さんもいました。
伝えるこちらもみんなのことが大好きなので本当は言いたくないのだけれど
心を鬼にして何度も何度も理由を伝え
少しずつ品質が改善されていきました。
今では新しくカゴ編みを覚える若い子が出てきたり
他の村の職人さんもmoilyでかごづくりをしたいと訪ねてくるようになりました。
そうすると職人さんたちは
「わたしたちと一緒に作るならきれいに作らないとダメだよ!」なんて言ってるから
笑ってしまいます。かわいい。
村の収入も平均2.5倍ほど上がり(2020年時)、出稼ぎに出かける人はぐんと減り
職人さんたちは家族と共に村で生活しています。

moilyのカゴには作った職人さんの名前をつけています。
手編みで作るカゴは、人間らしさがみえる面白さがあります。
いくつかの厳しい品質チェックをクリアしてきたカゴでも、カーブの加減や、素材の選び方、編む時の力の入れ加減、絶対に同じものはありません。
性格やその時の感情が感じられて面白いんです。

ぜひ、カゴを手に取る時、遠いカンボジアで、
職人さんたちが笑いながら、ハンモックを揺らして子どもをあやしながら、
穏やかにカゴを編んでいる様子を想像してみていただけたら嬉しいです。
職人さんについてはこちらから